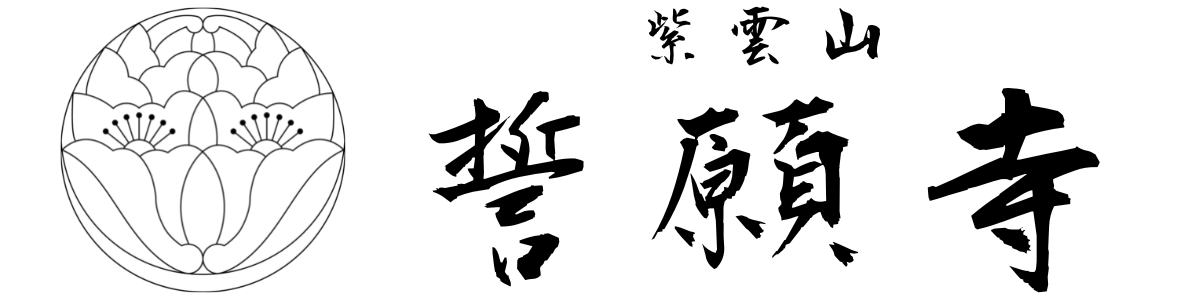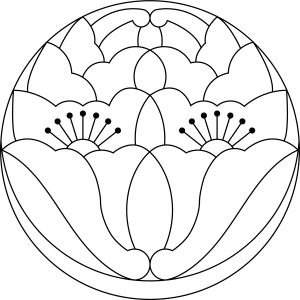日常勤行式のお話⑫~一枚起請文~
今回は、「一枚起請文(いちまいきしょうもん)」のお話です。
一枚起請文は、法然上人がお亡くなりになる二日前に残したお言葉で、弟子達への遺言となる教えです。
一人でも多くの方々にお念仏の教えの真髄が伝わるようにとの、法然上人の御心が拝察出来る、とてもわかりやすい教えです。
このようなお言葉です。
「唐土我朝に、もろもろの智者達の、沙汰し申さるる観念の念にもあらず。
また学問をして、念のこころを悟りて申す念仏にもあらず。
ただ往生極楽のためには、南無阿弥陀仏と申して、うたがいなく往生するぞと思い取りて申す外には別の仔細候わず。
ただし三心四修と申すことの候は、皆決定して南無阿弥陀仏にて往生するぞと思ううちにこもり候なり。
この外に奥ふかき事ことを存ぜば、二尊のあわれみにはずれ、本願にもれ候べし。
念仏を信ぜん人は、たとい一代の法をよくよく学すとも、一文不知の愚鈍の身になして、尼入道の無智のともがらに同じうして、智者のふるまいをせずしてただ一向に念仏すべし。
証のために両手印をもってす。
浄土宗の安心起行この一紙に至極せり。
源空が所存、この外に全く別儀を存ぜず、滅後の邪義をふせがんがために所存をしるし畢んぬ。」
意味は、
「私が説く念仏は、中国や日本の多くの学者たちがお説きになっている、心を集中して仏さまのお姿を想像する観念の念仏ではありません。
また学問をして、念仏の意味を理解してとなえる念仏でもありません。
ただ極楽浄土に往生するためには、南無阿弥陀仏と声に出してとなえることによって、必ず往生するのだと確信して念仏をとなえる以外、何も細かなことはありません。
ただし、三心、四修といわれるお念仏をおとなえするうえでの心構えがありますが、それも南無阿弥陀仏と口にとなえれば必ず往生できると思ううちに自然とそなわるのです。
もし、かりに私がこのほかにさらに奥深いことを知っているというようなことがあるならば、お釈迦さま阿弥陀さまの慈悲の心からはずれ、本願による救いからもれてしまうでしょう。
念仏を信じる人は、たとえお釈迦さまの教えをよく学んでいても、自分は経典の一文さえわからない愚か者と受けとめて、知識のない者と同じように智者ぶったふるまいをしないで、ただひたすらに念仏をするべきです。
以上に申し上げたことを、私の教えとして誤りがないという証のために両手印を押します。
浄土宗の信仰心の持ち方と、その実践についてはこの一枚の紙に記したことに尽きます。
私、源空(法然上人)が思うところは、これ以外にありません。
私の死後に、誤った考えが生まれるのを防ぐために、思うところを記しました。
建暦二年正月二十三日 大師在御判」
となります。
今回はここまでにして、簡単な解説は次回に続きます。